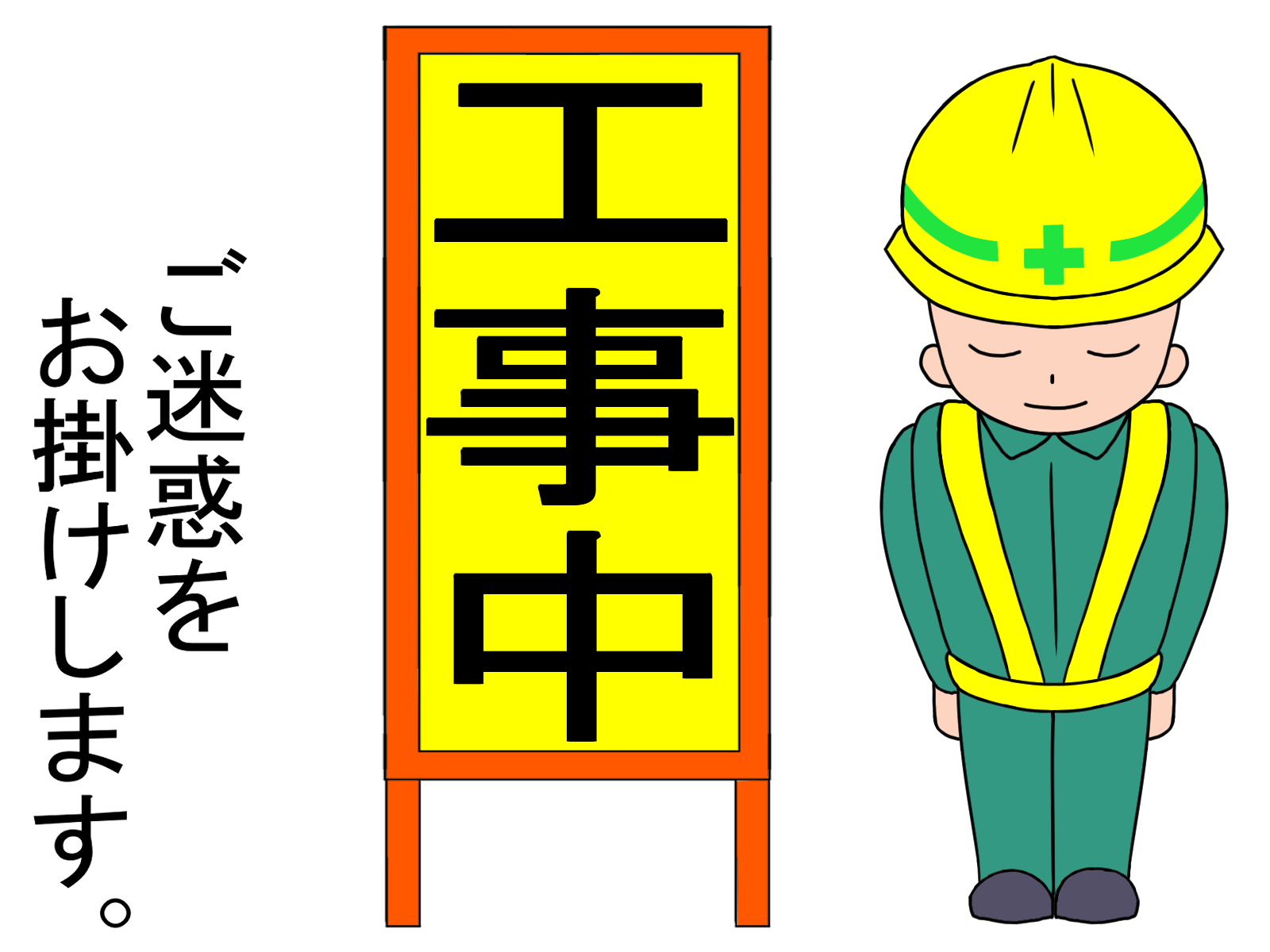当然のことながら、『ウルトラマン』(1966年)には、高度経済成長と時代の未来科学信仰が、『ウルトラセブン』(1967年)では、その高度経済成長の崩壊とベトナム戦争が、『ウルトラマンレオ』(1974年)には、UFOや念力、終末予言ブームが、それぞれに色濃く影を落としている。
そういった時代背景や、同時代時期に存在していた作品や文化などにも、評論対象物と同等か、それ以上に目を向けなければ、作品評論などは、そもそも成り立たないのである。
そしてそれは、その時代を生きていなかった者にとっては至難の業である。
もちろん筆者とて1966年生まれ。
第二期ウルトラでは現役の視聴対象者であるわけであり、ある意味筆者にとっての第二期ウルトラ論は、当時のターゲットを代表する、印象論からスタートしている論も少なくはないが、第一期論においては、まだ自我もなかったころの作品になるわけであり、その点においては、筆者は論を進めるにあたっては、可能な限り、60年代という時代を俯瞰するように努めている。
ウルトラがなぜその時代に生まれたのか、なぜその時代に存在していたのか。その時代の中で、なぜウルトラは生まれ出でたのか。
そこに向き合うだけの覚悟がなければ、ウルトラを見据えることは出来ないだろう。
現代では、ウルトラはいくらでもソフトで視聴できる環境だが、「木を見て森を見ず」と諺にもあるように、ウルトラだけを観てウルトラを語る行為は、様々な危険が伴うということを、静かに主張しておこう。
かなり長く話が逸れてしまったが(笑)
つまり、たとえば60年代中期から末期へ向けてという時代は、あらゆる意味で戦後が終わり、テレビ時代へと向かう中で、そのテレビを中心として、一気に表現の場所や機会を広げつつあった
ドラマ・バラエティ・歌謡曲・喜劇などをはじめとして、若者音楽としてのロック、グループサウンズや、大衆娯楽小説や社会派小説、前衛芸術やプロ野球やプロレスといったスポーツにいたるまで、ありとあらゆる娯楽を楽しむ余裕を、ようやく得た庶民にとっては、まさに無数の選択肢を前にした時代であったのである。
そんなさなかに、一人の青年がいた。
彼は売れないコント作家の卵として、はかま氏に支持していた。
明日も夢も、何も見えない時代の中で、彼はとにかく今日を生き抜こうと必死だった。
自分には、コントを続けていける自信がない、そう判断した彼は、『ウルトラマン』放映最中の円谷プロが、同時進行でNTV系列で製作していた『快獣ブースカ』(1966年)へ脚本を持ち込んだ。
『ブースカ月へ行く』『ブースカと七人の魔術師』と題された作品は、円谷プロの金城哲夫氏他による最終選考まで残った。
「三つ揃いのスーツに細身を包み、頭にハンチング、片手にアタッセケースを持ち、もう片手で傘をステッキのように突いて、チャップリンのような若者が現れた。市川森一だった。」
『金城哲夫 ウルトラマン島唄』上原正三著
その時の最終選考には、後に鬼才と呼ばれる、情念派脚本家・長坂秀佳氏も残っていたが、当時長坂氏は東宝の社員でもあったため、金城氏による「長坂氏は社員だから喰いっぱぐれはないだろう」という恩情により、市川森一氏の方の採用が決まった。
(この件で根に持ったのかは定かではないが、長坂氏はその後延々と、市川氏をライバル視するようになって、そこにはそこで、まことしやかに語られる様々なおもしろい逸話もあるのだが、それは本筋ではないので、またの機会に譲るとしよう)
その時から数年間、市川氏は円谷文芸部在籍の専属作家として、また、その後は外注作家として、様々な形でウルトラを支えていく事になる。
その市川氏の、ウルトラデビュー作こそが、本話『V3から来た男』であった。
この時期、円谷プロは、セブンと平行して「テレビ界初の一千万円ドラマ」と呼ばれた、文字通りフラッグシップのドラマ『マイティジャック』(1968年)をスタートさせて、円谷文芸部の長でもある金城氏はそちらへかかりきりになり、セブンは、残された上原氏と市川氏で取り仕切ることになっていった。
そういった体制の中で作られていった、セブン後半の物語群は、様々な形で、第二期ウルトラへ影響を残していくことになり、それはもちろん、歴史の定石どおりに、第一期ウルトラをしっかりと、正しく見据えなくては、第二期ウルトラを語る事などできないのである。
例えば本話が持っていた、キャラクタードラマとしての核は、そのまま『帰ってきたウルトラマン』(1971年)で市川氏が描いた、『ウルトラセブン参上!』の、梶キャプテンと加藤隊長の友情に「宇宙ステーションキャプテンの南廣氏」というキャスティングもそのままに、受け継がれていったりするのであるが、この二つのエピソードを、偏見なく俯瞰することで、第一期ウルトラと第二期ウルトラの違いが、定点観測で見出せたりもするのである。
本話に関しては、後年市川氏自身が「当時は自分が若すぎて、軍隊という組織を格好良く描きすぎた」というような発言を残しているが、本話で市川氏が試みた「レギュラーではないキャラクターを掘り下げて描く事で、相対的に、主人公チームの存在感を別角度から描き出す」は、その後第二期では、様々な作家によって常套手段化していくのではあるが、一方で、本話で描かれたクラタ隊長というキャラの存在は、地球防衛軍・ウルトラ警備隊という組織に、かつてなかった実存感を与えることに成功した。
筆者のこの分析が見誤りでないことは、他でもないメインライターの金城氏が、セブンの最終回を描くにあたって、重要なキーマンとして、クラタ隊長というキャラクターをドラマ内に配置したことからも分かるし、また、本話における市川氏の人間描写の巧みさを見た金城氏が、その後セブンにおいては、市川氏に対して、キャラクター個々に焦点を当てて、掘り下げて描く作劇を、統括者としての立場から、指示したということからも分かるだろう。
本話における、クラタとキリヤマ、そしてマナベ参謀による、大人な会話の巧みさは、これは市川氏ならではの技術である。
セブン後半に、プロデューサーとして参加した橋本洋二氏は、当時の市川氏を、台詞は上手いがドラマにテーマがないと評したが、台詞が上手いということは、すなわち人間造形が上手いということである。
30分ドラマというものは、凝縮された短編映画のようなものであるがゆえに、そこでの会話一つ、言葉遣い一つ、疎かにしてはならない。
逆を言えば、そこで台詞が上手いということは、台詞を用いての人間描写や状況描写が巧みだというわけであり、つまり、一つの台詞が有する情報量が、様々な意味で多いということでもある。
これは、凡百の作家が二つも三つも台詞を消費して行う描写を、必要最低限の台詞量でこなせるという、技術論的に立証される、作家スキルの高さの表れなのである。
また、個人的心象を述べさせてもらうならば。
橋本氏が評した「テーマがない」という市川氏評にも、実は筆者はかなり懐疑的である。
ドラマが必ずしも、テーマを内包せねばならないという義務は、実は何処にもない。
第一期作品にも、数多くのメッセージが込められている作品は多かったかもしれないが、実は「テーマ」と「メッセージ」、「教訓」と「風刺」、「教育ドラマ」と「寓話」は、全て別物であり、それらの存在価値を微妙に意図ずらししたのが橋本イズムであるのだ。