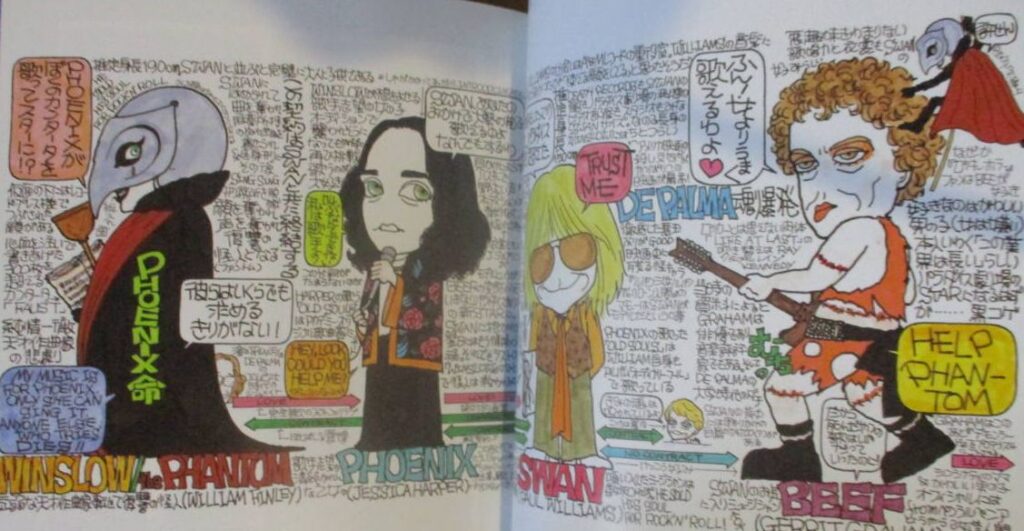この回では、大映出身で円谷英二に誘われて円谷プロ入りした的場徹氏が、『ウルトラマン』(1966年)の制作1・2・3話以来の特撮監督を務めた。
そして本編監督は鈴木俊継氏。鈴木監督は、そもそもは東宝の契約俳優出身という珍しい肩書きの持ち主。
円谷英二監督に師事して『ウルトラQ』(1966年)に、特撮助監督として参加した。
その堅実な作りと、丁寧かつ迅速なスケジューリングは、初期の円谷のクオリティと過酷な製作体制の、両者のバランスを上手く支えていた。
鈴木監督は後年、円谷社員監督として、『ミラーマン』(1972年)の『消えた超特急』や『月面怪獣キングワンダーとの死闘!』『ファイヤーマン』(1973年)の最終回『宇宙に消えたファイヤーマン』『トリプルファイター』(1972年)などで円谷プロを支え続けた。
ちなみに鈴木監督の奥様は、第一期ウルトラのスクリプターでもあり、実相寺昭雄監督の自伝小説『星の林に月の船』で、ヒロインのモデルになったのではないかと一時期噂されていた宍倉徳子氏。
このように、第一期の円谷作品は、的場特撮監督や鈴木監督のように、円谷英二監督が直接招いたスタッフが、飯島敏宏・実相寺昭雄などといったTBS演出部出向組と共に、作品のクオリティを支えていたのである。
しかし、実情はというと、上で名前が挙がった実相寺監督の著書『星の林に月の船』の描写ではないが、どうしても円谷社員監督よりも、親会社のTBSから出向してきた演出家の方が、手厚く扱わなければいけない傾向は高かったようで、例えばそれは、『ウルトラマン』や『ウルトラセブン』(1967年)において、劇伴(BGM)の新規収録が、実相寺・飯島といったTBS演出部監督の監督作品に併せて行われていたり、TBS組監督のスケジュールや予算のしわ寄せがどうしても、円谷組の監督(例えば今回の鈴木監督)の回に流れ込んだりといった状況を生んでしまう現実はあったらしい。
(例えば『ウルトラQ』で『カネゴンの繭』『鳥を見た』等の、ジュブナイル傑作を撮ったTBS映画部の中川晴之助監督などは、その使用フィルムの多さから「フィルム食いのハルゴン」などと呼ばれていたらしいし、『怪奇大作戦』(1968年)での実相寺昭雄監督の予算の圧迫の仕方は今では語り草である)
また『ウルトラマン』において、ウルトラマンのマスクがA、B、Cと3タイプに分かれていて、徐々に完成度が高くなっていったことは、ファンなら誰もが知っている事実だが、そのまさに「番組の顔」ともいうべき、ウルトラマンの造形が新調される回は、14話『真珠貝防衛指令』30話『まぼろしの雪山』と、どちらも実相寺昭雄・樋口祐三と、TBS演出部の作品であることも、単なる偶然ではないのかもしれない。
夢の世界・夢工場と呼ばれるテレビの世界であっても、それは業務であり社会の仕事であるから、そこでの制作体制は常に、元請のTBSと、協力業者(下請)の円谷という図式の中で行われていく。
そのしわ寄せが円谷に集まるのは、これはどんな業界であっても当然であり、大事なのは、本来の視聴者たる子ども達に、その苦労やねじれが見えないように気配りすることである。
上記したように、制作体制内においての、円谷スタッフとTBSスタッフの扱いの差は、セブンでは『ウルトラマン』時代よりもはっきりとした形で現れることになるが、それはつまり、予算やスケジュール等の管理体制そのものが、セブンの時代には過酷で過密になっていたことの現われであろう。
その片鱗を示すエピソードが、本話にも存在する。
ここで登場するイカルス星人は、そもそも7話の『宇宙囚人303』に登場するキュラソ星人としてデザインされたものだったのだ。
確かに、最終的にイカルス星人とされたデザインに見られる、濛々と蓄えられた髭や屈強そうな肉体は、古い洋画に出てくる「囚人」のイメージにこそ相応しい。
ウルトラシリーズの怪獣・宇宙人は、第一期においてはまず、監督・脚本家とデザイナー・成田亨の間で打ち合わせがあり、その上で成田氏がデザインを起し、造形家・高山良策氏によって、最終的な着ぐるみが造られるという経緯を辿る。
イカルスとキュラソの交代に関しては、『ウルトラマン』開始以来、ずっと保たれてきたこの流れの、どこかで不具合が生じてしまった為、高山氏の造形の完成スケジュールと撮影のスケジュールの間で、ねじれが発生してしまい、結果として起きてしまったというわけである。
脚本・演出がどうであれ、ウルトラシリーズにおいては、まず、その話で登場する怪獣こそが財産であり要なのであることは、これは動かしがたい基本精神であるが、粗製濫造と喧騒にまみれた第二期ウルトラの時代ならいざ知らず、黄金の第一期、しかもセブン製作開始間もない第10話(制作NO.は7話・8話)において、このようなトラブルが起きていたことは、セブン当時の制作状況のストレスが、当初から相当なものであったことが想像できる。
ウルトラがその制作環境において本当の意味で、時間的・予算的に恵まれていたのは『ウルトラQ』制作時期だけであったのかもしれない。
『ウルトラマン』は当初の体制では、怪獣の着ぐるみやメカニック等で、前作や東宝からの持込による運用が目立つし、中盤からのスケジュールの過密ぶりは、絶好調の波に乗った番組自体を、打ち切らざるを得ないほどに現場を追い詰めていたのだ。
『ウルトラセブン』は更に、窮状の中で制作されていたのであろう。
そのしわ寄せは様々な形で、円谷生え抜きの演出家やスタッフに襲い掛かったのではなかろうか。
夢がいつでも、夢に溢れた工場から出荷されるわけではない。戦場のような、ギリギリの状況の中からこそ、生み出される夢もあるのだ。
追い詰められた人間から生み出されるエネルギーが、セブン全体を包み込んでいたのかもしれない。
ちなみにこの回の撮影では、アンヌ役の菱見百合子さんが、撮影の合間にはしゃぎすぎて、ロケセットとして借りていた邸宅のシャンデリアを、見事に割ってしまい、その弁償でシャンデリア代がギャラから天引きされたという有名な逸話もある。
菱見百合子さんはこのペナルティとして、次話『魔の山へ飛べ』では出番を削られて謹慎扱いとなってしまった。
『魔の山へ飛べ』は、ダンが一時的とはいえ、死亡してしまうエピソードでもあり、後にダンと親密な恋愛関係に発展するアンヌが不在というのは、シリーズ構成を後から検証していったときには落とし穴になってしまうのだが、菱見さんはそれまでにも、監督やスタッフの忠告を無視して、二日酔いで現場に現れたりといった奔放ぶりが目立っていたために、特に満田かずほ監督が堪忍袋の尾を切らせた結果となり、今回のペナルティに発展したようだ。
このエピソードなどは、少年時代にアンヌ隊員に胸をときめかせたファンだけではなく、その後に描かれた『私が愛したウルトラセブン』(1993年 脚本・市川森一)などを観た後年のファンにとっても、ショッキングな逸話なのかもしれない。
アンヌは清楚で華麗な、ウルトラ少年の憧れの的であったと同時に、当時の円谷スタッフにとっても、マドンナであり神聖なアイドルであったのだろうという、セブンファンの幻想と夢を、無碍もなく打ち壊してしまうエピソードだからである。
しかし、誤解しないでいただきたいのは、筆者は何も今ここでこのような逸話を書き記すことで、ファンの夢を打ち砕くことを楽しむような意図はないし、菱見さんの名誉やイメージを壊すことを目的としているわけではない。
「イメージと実像が違う」だけで言えば、純朴で生真面目さを前面に押し出していたダンの森次浩司氏だって、セブン放映当時にはもう結婚されていたのだ。
ここで大切なのは、今まで書いてきたような、製作予算的・スケジュール的に劣悪な製作環境や、生臭い会社の上下関係がもたらす製作体制の影響、そしておよそキャラのイメージとはかけ離れた実像を持つ俳優たち。