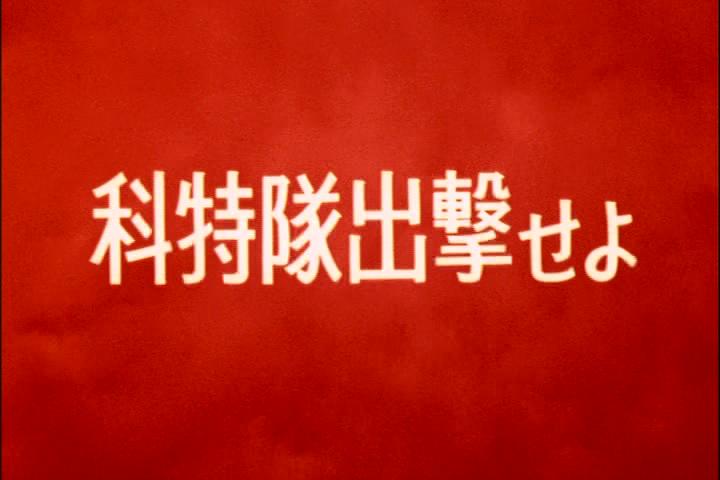Joe David Brownの小説『アディ・プレイ』(原題:Addie Pray)を原作としたこの映画は、古き良き1930年代のアメリカを舞台にして、既にこの頃名優であったRyan O'Nealと、その実娘であるTatum O'Nealの二人が、行きずり会った、中年男と少女の詐欺師コンビを演じて描かれる、ロードムービーであった。
そこには、アメリカンニューシネマに顕著だった、政治性も社会性も思想性も希薄ではあったが、当時まだ10歳にして、事実上父の役を食ってしまう、聡明でマセた少女詐欺師としての、存在感と演技力で、ヒロイン・アディを演じたTatum O'Nealは、その年の第46回アカデミー賞で、史上最年少で助演女優賞を獲得したほどであった(余談だが、映画で大ヒットした『ペーパー・ムーン』は、翌1974年にアメリカでテレビドラマ化されたが、そのドラマシリーズで、Tatum O'Nealが映画で演じたアディ役を担当したのは、『タクシー・ドライバー』出演前の、無名時代の11歳の頃のJodie Fosterであった)。
ここでも(前回の『バージンブルース』の相似形のように)主人公の中年男は、少女詐欺師に対して「大人になっても、男を騙す女にはなるなよ」と言い放つ。
大人の男の願望の押しつけ。そう言い切ってしまえばそれまでだが、それは日米双方共に、男性社会から、まだ社会の深遠さを知らないままの少女達に対する、悲しいまでに切実な、悲願を託したイニシエーションでもあったりするのだ。タイトルになった「紙の月」は、野坂昭如氏の『火垂るの墓』の蛍のように、虚構の中にしかない輝きを、少女に与え照らすのである。
ここまでの、70年代の日本の映画に登場した「妹」達と、同時期のハリウッド映画に登場した「少女」達との相似性は、共に現実逃避的で、郷愁や、男性社会原理の理想論の押しつけ的な立ち位置でありながら、それを求め、それを願い創る男性達に対して、当の少女達が「どこにも逃げ場なんてない。どこにも、貴方達が求める存在はいない」という「結論」を、突き付けて去っていくという点で共通している。
「その結末」は、誰を以てしても覆すことは出来ない不文律として、創作表現の世界を支配し続けるのだが、70年代も進み、徐々に世界が、社会が「ロリコン」的なる表現を持ち出しつつあるタイミングで、「少女に託した、切なすぎる希望論」は、一つの突破口を迎える。
今やロリコン文化史を語る時、外すことが出来ない写真家・清岡純子氏が、そのエポックとなる少女ヌード写真集『聖少女 Nymph in the Bloom of Life』を出版する直前の1976年、ハリウッドで制作、公開されて、その後日本でも大ブームを巻き起こした映画に、『がんばれ!ベアーズ』(原題:The Bad News Bears)という作品があった。
主演は『ペーパー・ムーン』と同じくTatum O'Neal。13歳になった彼女は、今度は病んだアメリカ社会の郷愁の道具に使われることもなく、疲れ果てた中年男性の願望を背負わされることもなく、むしろ、こちらの映画の主人公(本作でも、もちろん大人の男性だが)が、失い手放した過去の恋愛の残像が、溢れんばかりのバイタリティと「元気」を引っ提げて再登場する、それがTatum O'Nealの役どころなのだ。
「女は絶対に関与できない、男性社会のカリカチュア」であるはずの、野球のグラウンドというベースを舞台に、Tatum O'Neal演じる美少女天才ピッチャー・アマンダが、問答無用の元気と活力で、弱小落ちこぼれチームを勝利に導いていくという物語は、構造としてはありきたりではあるが、「妹」「聖少女」を求め過ぎて、閉塞し過ぎた日米双方の「壁」を、ぶち破るには充分な破壊力を持っていた。
だからであろう。既に日本の野球漫画界では、この人ありと言われていた、水島新司氏の『野球狂の詩』の、連載正式週刊化に当たって「日本プロ野球初の女性ピッチャー」が登場したり、TVドラマでも、同じく少年野球を題材にとりながらも、こちらはチームを率いる監督が、女性(林寛子)であるという設定の『がんばれ!レッドビッキーズ』が放映されたりなど、本作の和製フォロー作品が1978年前後に集中した。
ブームの火付け役になった『がんばれ!ベアーズ』も、すぐさま『がんばれ!ベアーズ特訓中』(原題:The Bad News Bears in Breaking Training 1977年)や(こちらは、米国以上に熱狂した日本へのサービスとセールスを兼ねた)『がんばれ!ベアーズ大旋風 -日本遠征-』(原題:The Bad News Bears Go to Japan 1978年)等が次々作られたが、二作目以降には、肝心のTatum O'Nealが出ていないため、それらは望み通りの大ヒットとはいかないまま終わっていった。
「少女のバイタリティこそが、どんな複雑な社会問題や、男性大人による世界構造よりも、強くて純粋である」
これは、後に語る80年代性の問題と併せることで、ようやくロリコンブームの本質が見えてくる鍵になっている。