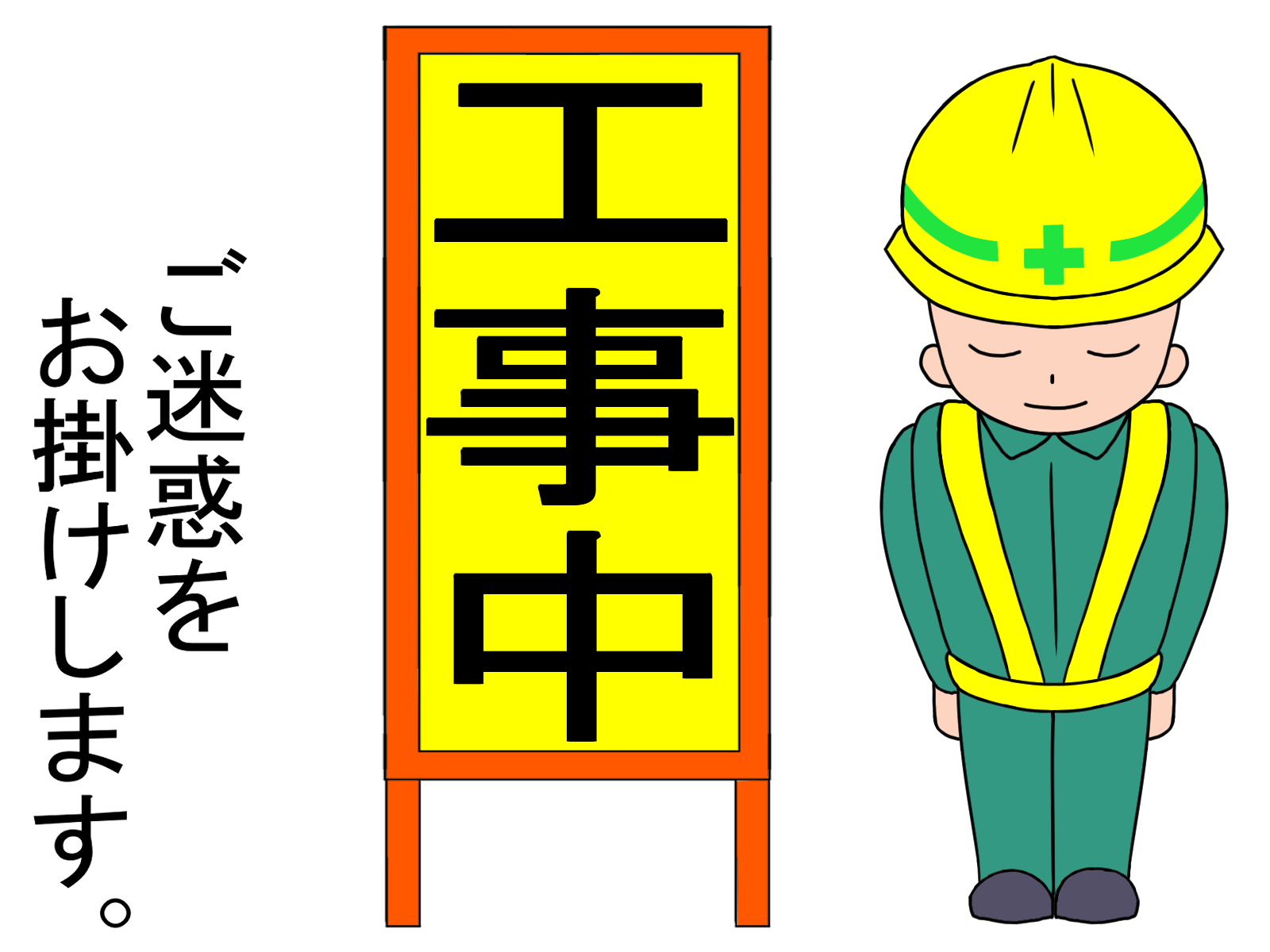しかし、ドラマ化されてから、新たに描かれた新作では、主人公のキャラクターが全く異なっているのだ。
絵柄は同じ。谷口氏の仕事に、手抜きも変化もなく、デザインも変わらない。
しかし、肝心の中身が、全くの別人になっているのだ。
過去に愛した女性を想い、思い出の鎌倉で食事をしながら、季節外れのトンビに自分を重ねてしまう主人公は、もうそこにはいなかった。
新作になってからの井之頭五郎は、コロコロ表情を変え、思いついたことをすぐ口に出して言葉でアウトプットし、いざ料理を食べれば食べたで、喜びはしゃぎ、「コバラベリー」だの「なくてけっこー コケコッコー」だの寒いダジャレを言いまくりながら、食べ物で失敗することもなくなり(要するに、企画物として内部でタイアップが成立しているため、1巻の頃のハンバーグ屋のような失敗談が描けなくなった)、ただただ、食った料理を褒めちぎるだけの漫画と化していた。
じゃあ『孤独のグルメ』らしさは全くなくなったのかといえば、あるよと言えることは言えるのであるが……。
「あちゃあ またしくじっちまったぁ イモだらけになってしまったぞ」
「なんだ この おもちゃっぽい味」
(食べ過ぎて)「いかん いかん」
「持ち帰り…… そういうのもやっているのか」
どれもこれも、1巻のあちこちで観た、昔からのファンならずっとネタにしてきた名台詞や印象深い展開のセルフコピー。1巻と同じ台詞が、外見は同じだが、中身は全く異なってしまった井之頭五郎から、発せられてる気分になる。
挙句には、飲み屋で絡んできた酔客にアームロックをかけるところまでを含めて、「1巻でウケた部分を、マーケティングリサーチで分析して、忠実に再現しました」を、やってしまっているのだ、この2巻は。
要所要所のラストのコマには、抒情的な展開を挿入したり、夜の繁華街の路地裏で煙草に火をつけたり、いろいろと「hard-boiledで純文学」っぽい演出もしているのだが、今の筆者にはどこか虚しい(と、銀座のハヤシライスがなくなっていた時の井之頭五郎の物言いを真似してみる)。
なぜか。
答えは簡単だ。
この2巻は、「ドラマ『孤独のグルメ』コミカライズ」だからだ。
要するに、『孤独のグルメ』は深夜ドラマが大ヒットして注目されたため、そっちから入ってきて、漫画版にも目を付けた人が多い。元々が純粋な作家性からきている表現ではないから、久住氏自身からすれば、ドラマ版での、主人公役の松重氏の演技やリアクション、芸風を、そのまま漫画版で再現したという、シンプルな構造論がそこにはある。
しかし、中身を全く松重氏にしてしまうのも、漫画としては1巻と乖離しすぎてしまう。
何度でも言うが、久住氏がクリエイター気質であれば、そこで「自分の中だけの井之頭五郎像」を、延長追加して挿入すればよかったのであるが、久住氏はあくまでプロデューサー気質であるがゆえに、新たな井之頭五郎像を作る事よりも「松重氏の演じたドラマ版井之頭五郎の芸風に合わせることで、ドラマから来た読者をキャッチする」と「1巻でウケた、名台詞や名シーンをそのままもう一回使うことで、漫画時代からのファンには『孤独のグルメ』アルアルとして、喜んでもらおうと」と、一挙両得を考えたのだ。
一つのコンテンツを総合的に独断で舵取りする、一人のプロデューサーの考え方としては悪くない、決して悪くないぞ(ここもまた井之頭五郎風)。
ヒットドラマコンテンツの一つの関連グッズのあり方としては、満点の選択肢だろう。
しかし、『孤独のグルメ』という作品を作品として愛し、そこで黙々と、食と向き合っていた、井之頭五郎という主人公を人として愛していた読者にとっては、これは残酷な仕打ちであろうと、言わざるを得ない。
テレビで流行っているロボットアニメの、漫画化とは意味が違うのだ。
しかし。
「そこ」も、久住氏の狙いだったと受け取ることは可能だろう。
確かに80年代までは、テレビのドラマやアニメがコミカライズされ、しかしそもそもそのドラマ自体、漫画の原作が最初にあったのに、そこを跨いで「もう一つの漫画」が出来てしまうものだから、読者はいろいろな意味で戸惑いながらも、全てを受け入れてしまうしかないというような現象が、『仮面ライダー』『マジンガーZ』『デビルマン』等の作品で頻繁にみられていた。
ドラマ版を挟んだ、2冊の『孤独のグルメ』の関係は、その構造のパロディであり、だから久住氏は、やはり何があっても、サブカルチャー全盛の70年代から80年代に、今もまだ「表現のプロデュース」という形で、パロディを仕掛け続けているのかもしれない。